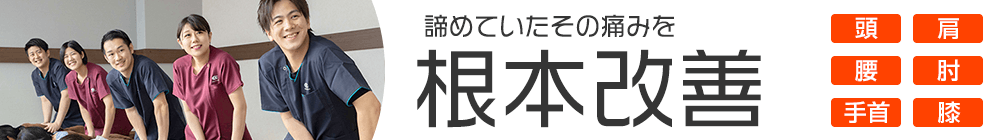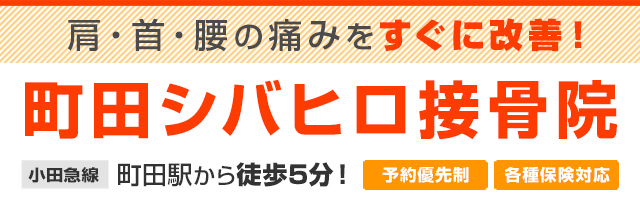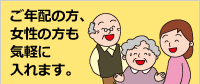肉離れ

こんなお悩みはありませんか?

走ったら突然太ももやふくらはぎに痛みが出た
ステップやジャンプをすると太ももが痛い
重い物を投げたときに腕や背中、胸が痛くなった
運動したら、痛みとともに皮膚が青くなった
ふくらはぎから「ブチッ」と筋肉の断裂音が聞こえた
スポーツ中や日常での動作の中で、突然太ももやふくらはぎから「ブチッ」という音が聞こえ、激痛が走って動けなくなった場合は肉離れの可能性があります。筋肉が断裂した音であり、非常に強い痛みを生じるものです。
肉離れで知っておくべきこと

肉離れを起こすと、筋肉の繊維が損傷し、筋肉の周囲の血管も同時に傷つき、皮膚の下で出血が起こります。初期の対応として、RICE処置を行うことをお勧めします。
安静(Rest)
歩いて痛みがある場合は、なるべく歩かないようにし、松葉杖を使用するなどして、痛みが出ないようにしましょう。
アイシング(Icing)
アイシングは通常、氷のうを使用して、1回あたり15分~20分間行います。寝るときに冷湿布を貼るのも効果が期待できます。
圧迫(Compression)
軽く圧迫することで、筋肉の動きを制限し、出血量を抑えることができます。
挙上(Elevation)
足の下に枕やタオルを入れて、体より少し高くしてあげてください。
症状の現れ方は?

典型的な症状として、まず肉離れを起こした瞬間に「ブチッ」や「バチッ」といった筋肉の断裂音が聞こえ、その直後から痛めた筋肉に強い痛みが生じ、歩くことが困難になります。ただし、肉離れを起こした際に必ず断裂音が聞こえるわけではありません。
肉離れを起こした部分を押すと強い痛みがあり、また筋肉に対して曲げ伸ばしの動作や収縮運動を行うと、さらに強い痛みが表れます。やがて切れた部分に腫れや皮下出血(あざ)が見られるようになります。損傷の程度によっては、筋肉の切れた部分がへこんでいるのが見た目でわかることもあり、触れてみるとその部分がへこんでいるのが感じられることもあります。
その他の原因は?

肉離れの主な原因としては、筋肉の強い収縮と同時に、逆に引き伸ばされるような力が加わることによって起こります。つまり、筋肉に急激な負荷がかかり、筋肉が耐えられない状態になった際に発生します。例えば、ダッシュ中に急に止まったり、ジャンプからの着地などの動きで起こりやすいです。
また、水分が不足すると筋肉に必要な水分も不足し、筋肉の柔軟性が低下してしまいます。十分に水分が行き渡らず、筋肉が硬くなっているときに急激な運動を行うことでも、肉離れを引き起こしやすくなります。
他にも、ウォーミングアップを十分に行わなかったり、筋肉に疲労が蓄積している状態、加齢なども肉離れを引き起こす原因となります。
肉離れを放置するとどうなる?

肉離れは、動きの激しいスポーツなど筋肉を酷使することで発症しやすい症状です。
肉離れを引き起こす原因として、
1.「筋力不足や筋疲労」
2.「筋肉の柔軟性の不足」
3.「天候の変化」
が挙げられます。
また、肉離れは完治の判断が難しいため、回復していない状態で放置して無理に患部を動かしてしまう方も多くいらっしゃいます。
もし肉離れを放置してしまうと、肉離れを起こした筋肉から出血し、血腫(内出血した血液のかたまり)が肥大化していきます。その結果、断裂した筋繊維同士が離れてしまい、再び合わさるまで時間がかかります。
また、仮に合わさったとしても、元の筋肉の繊維よりも弱い結びつきになってしまいます。そのため、肉離れが完治するまでに時間がかかる上に、「癖」になり再発する危険性もあります。
肉離れが癖になってしまうと、スポーツで満足のいくパフォーマンスが出せなかったり、痛みで歩くのが辛くなったりと、日常生活にも悪影響を及ぼします。そのため、少しでも早く施術を受けていただくことを強くおすすめします。
当院の施術方法について

急性期には応急処置を施術の中でしっかりと行います。状態によってアイシング、圧迫固定、テーピングなどを行います。
急性期が過ぎた後は、肉離れを起こした部位が硬くなり、柔軟性を失ってしまっているため、手技療法、ストレッチ、超音波施術を行い、再発を予防し、日常生活に支障が出ないように回復を目指します。
また、肉離れが起きやすくなってしまっていた根本的な原因に対して、インナーマッスルトレーニングや骨格矯正なども回復に合わせて行っております。
肉離れの状態を放置してしまうと、パフォーマンス低下や固さが残ってしまうことがありますので、放置せず、施術を受けにご来院ください。
改善していく上でのポイント

痛めた部位は安静にすることが大切ですので、できるだけ動かさないようにしましょう。最低限動かさなければならないタイミングでは、できるだけ加重を控え、動かす範囲も少なくすることが重要です。
痛めてすぐや、痛みが強く出る場合は炎症を抑えるために冷やしましょう。その後、数日が経ち痛みが減ってきた場合などは、温めることで負傷した部位の血流を促進し、回復を早めることが期待できます。
また、日常生活で痛みが出なくなったからといってすぐに早い動きや強い負荷をかけてしまうと、再発するおそれがあります。普通に歩く、早歩き、階段を上り下りしてみるなどして、徐々に痛みの出ない範囲を探していきましょう。
監修

町田シバヒロ接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:神奈川県相模原市
趣味・特技:野球観戦